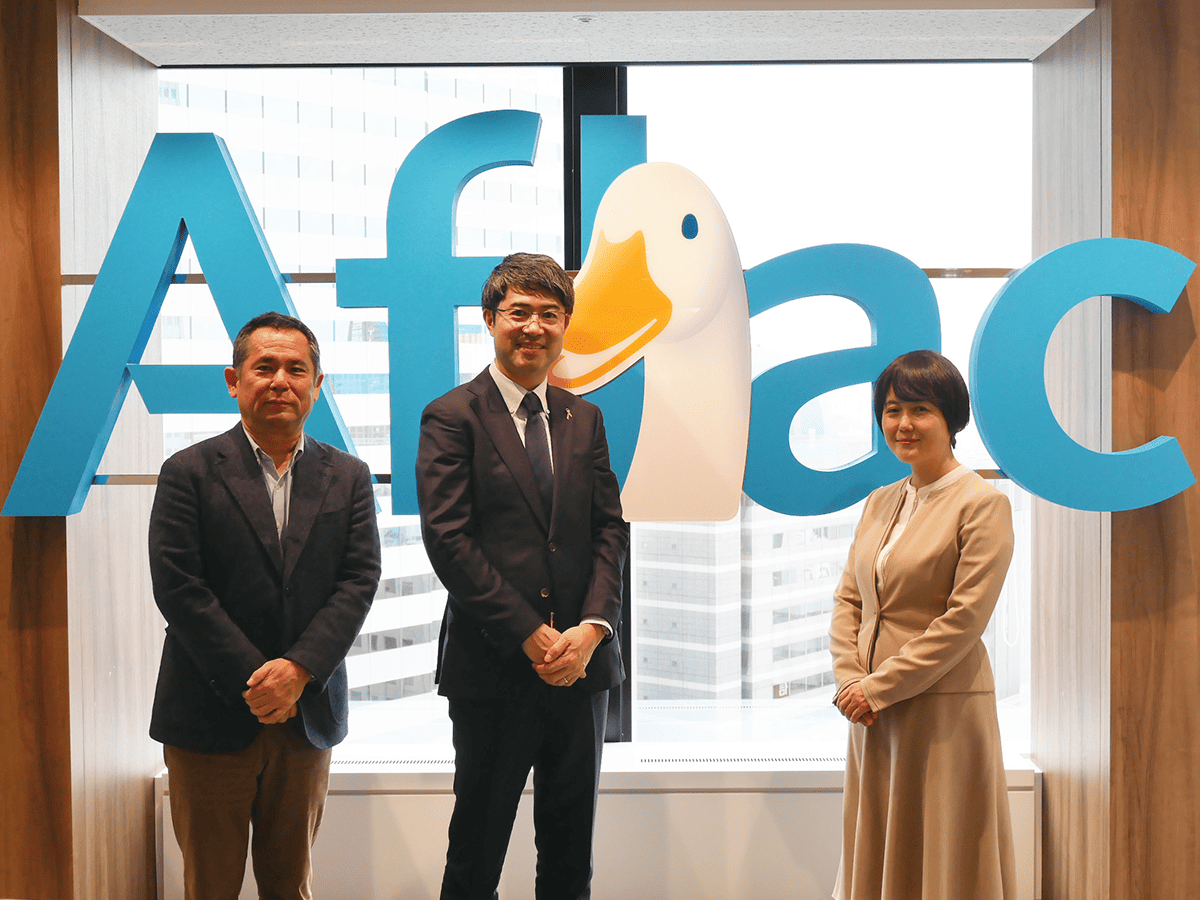導入実績
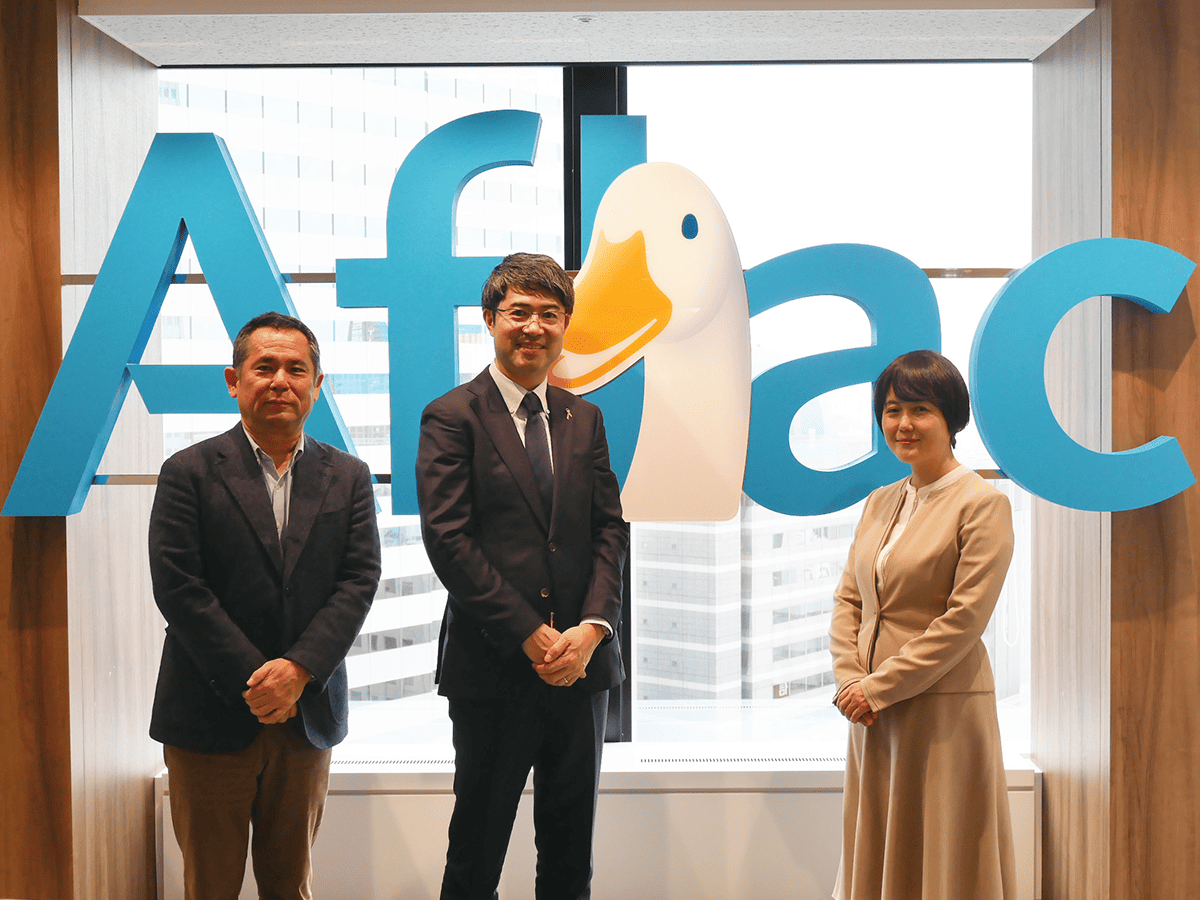
アウトソーシングの活用による業務効率化の実現とより付加価値の高い業務への人的リソースのシフト
2018年9月サービス開始

アフラック生命保険株式会社 様
保険業
約5,000人
ご利用サービス
人事・給与・勤怠・申請
2017年当時、同社は翌年の人事制度改定とシステムのサポート期限を迎える中で、
新経営計画による全社的なリソースの効率化を検討されていました。
人事業務の中でも特に定型業務を多くかかえている給与厚生業務については、
効率化による効果が大きく期待できると判断され、エイチアールワンにアウトソーシングすることを決定されました。
2018年のサービス提供開始から現在まで、そうした戦略的な人的リソースのシフトを背景に、
先進的な人事戦略を数多く進められており、またそうした効果を積極的に発信されています。
アフラック生命保険株式会社様 インタビュー
アフラック生命保険株式会社
常務執行役員(人財マネジメント戦略・経営戦略担当) 伊藤道博様
インタビュアー:エイチアールワン株式会社 武谷、國重
アフラック社の目指す先進的な人事戦略とその重要性
90年代後半から2000年前半にかけ、国内でも職務給制度の導入が流行っていましたね。当社も2002年に職務グレード体系を導入し、その後また職能的な制度に戻りましたが、上手くいったこと、いかなかったことなど、当時の経験を活かしながら、2021年に改めて職務等級制度を導入しました。(伊藤様)
評価制度も変えました。人事というのは、等級制度、評価、育成、採用、配置など、全体に一貫性を持たせることが大事です。過去の経験にも学び、細部にも「魂を入れる」ようにしています。今回の制度改革の目的は「主体的なキャリア形成を支援する」ことですので、どのようにすれば社員の主体性を刺激できるか、徹底的に考える必要があります。評価制度についても、主体性を尊重する評価項目を入れたり、相対評価は馴染みませんから、絶対評価に変えたりしました。他にも、例えば、職務記述書(Job Description(以下、JD))も単にグレードを決めるための手段と考えると、非公開でもいいのではないか、となりますが、それでは社員の主体性の刺激には繋がりません。JDを公開することで、社員は目指すポストのJDを見ることができ、必要とされる能力やスキルとのギャップに気づきます。この気づきこそが、主体的なキャリア形成の第一歩になります。このように、一つひとつの制度や仕組みに一貫性を持たせるよう徹底しています。(伊藤様)
経営的な観点での課題整理から始めました。将来の経営環境や経営戦略を踏まえ、どのような人事であるべきかが起点です。環境変化が激しく、保険業界の競争も激化している中にあっても勝っていくためには、現場にいる社員一人ひとりが、主体的に考え行動し、活躍できる環境を作っていく必要があります。全てを上から指示していくのではなく、より迅速に現場で起こっていることを現場で判断して対処していく必要があります。にもかかわらず、昇給や昇格基準や要件を会社が指示するようでは、社員の主体性は育まれません。意欲と能力をベースにすることで主体性を刺激し、自らキャリアを築いていける環境をつくる必要がある。結果として、「職務等級制度」を導入すべきではないか、という議論が生まれます。次に、職務等級制度を丁寧に運用するためには、人事権を現場サイドに移すべきではないか、という問いが生まれます。そうなると人事と現場の役割や関係性はどうあるべきか、人事のオペレーションはどうあるべきか、という次の問いが生じてきます。このように順次生じる課題を、一つひとつひとつ、一貫性を保ちつつ解きながら、制度設計していきました。(伊藤様)
確かに私もそうです。新卒で入社し、人事以外にも、営業や支払部門など、多くの異動を経験してきました。苦労もありましたが、結果的に自分のキャリアに活きていますね。おっしゃる通り、主体的なキャリア形成といっても、完全に本人任せにすればよいというものでもありません。会社として、社員に気づきを与え、育成を支援することは当然に必要ですし、会社主導での人事異動を行うこともあります。とはいえ、会社主導の人事異動においても、本人の自己申告や希望がベースになりますから、自分がどうありたいか、何をしていきたいか、ということは、これまで以上に社員に考えてもらうような働きかけが大事になっています。(伊藤様)

現状は、ポスティングによる異動よりも、部門の統括担当役員の判断をベースに異動や登用を判断することが多いです。職務等級制度を厳格に運用しているので、ポジションが変わることで、グレードが上がることもあれば、下がることもあります。(伊藤様)
そのジレンマはありますよね。しかし全社員にとって完璧な制度というものは存在しないということを考えると、一旦、経営判断として決めたのであれば、感情論に流されることなく正しく運用していくべきだと考えています。そうしないと、別の不公平が生じてしまうからです。当社の場合は一度グレードが下がった社員が再度登用されるケースも多いです。グレードが下がっても、再度チャンスがあることを示すことが納得感を高めるのだと思います。(伊藤様)
職務等級制度の効果
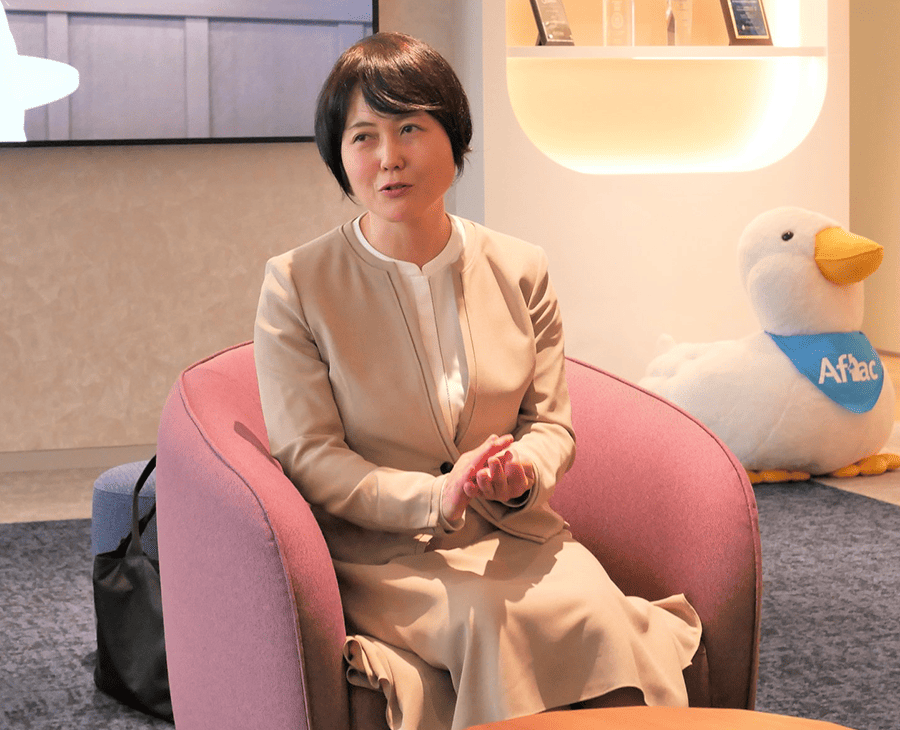
JDの見直しは必要に応じて随時行なっています。業務分掌の変更や、中期経営戦略や経営戦術を踏まえ、部署の役割が変更になるタイミングで随時見直ししています。当社は毎年1月に大型の組織改編があって異動が増えるので、その時は大変ですね。(伊藤様)
確かに大変ですが、見直すのは組織のリーダーの仕事でもあります。なぜなら、JDは全社公開され、多くの社員が閲覧しますので、丁寧に作っていなければ、ポスティングなどで良い人財が集まらないことになります。キャリア採用や人財育成にも使用します。つまり人財マネジメントのベースになるのがJDですから、これをどう作るかは組織のリーダーにとり、とても大事なことです。人事はJDの意義や作成方法をレクチュアし、伴走することが仕事になります。ちなみに私も、担当部署の部長や課長のJDを、期待を込めて作成しています。(伊藤様)
過去、当社でも同様のことが起こりました。やはりJDを作成することが目的にならないようにすることが大事ですね。先ほどお話ししたように、JDは、人財マネジメント制度の根幹です。JDをもとにグレードを決めるだけでなく、JDをもとにポスティングを実施したり、採用、育成、評価の参考にしたりします。JDを全社に公開しますから、他部署と比較されますし、各部では真剣に作成せざるを得なくなります。作成の手間はかかりますが、それ以上の価値は大いにあると考えています。(伊藤様)
職務等級制度の導入効果として大きくは2つあります。まず社員の観点で言えば、「主体的なキャリア形成」への意欲が高まったことがあります。当社には「キャリア開発計画書」というものがあります。将来目指したいキャリアに向けて、社員が能力開発の計画を立てます。この計画書の作成は任意にしています。強制しては、「主体的なキャリア形成」と言えないからです。それでも、実に75%もの社員が作成しています。さらに残り20%は今後作成予定と回答していますので、9割以上の社員がキャリア自律に向けた一歩を踏み出していることになります。これは大きな変化で、10年も経過すると、大きな違いになっていると思います。(伊藤様)
その通りです。「Aflac Cafe」と呼んでいる制度ですが、自己啓発のために自由に使える支援金を年10万円まで支給しています。(伊藤様)
必要に応じて会社主導の異動があるということは、制度導入時から一貫して説明しています。また、異動というのは希望すれば成立するものではありません。本人もまた、“選ばれる人財”にならなければならない。そのためにも、まさに主体的に、スキルや能力を磨き、実力を高めていく必要がある。そういうことをしっかり伝えています。(伊藤様)
職務等級制度の導入の2つ目の効果として、組織側の観点で言えば、配置や組織改編の柔軟性が高まったことがあげられます。従来は、昇格や登用のタイミングと組織改編のタイミングを合わせたり、昇格数を調整したりと、人事制度にビジネスを合わせることもありましたが、今はいつでも組織を変えることができますし、リーダーの登用・変更も随時可能なため、経営のスピード感が従来とは全く異なります。また、部門に人事権を渡したことで、社員への向き合い方が丁寧になっています。社員の育成や評価、配置などに、真剣に取り組むようになりました。社員に対する説明責任は、人事でなく、部門にあるからです。(伊藤様)
BPO(Business Process Outsourcing:ビジネス・プロセス・アウトソーシング(以下、BPO))検討の経緯
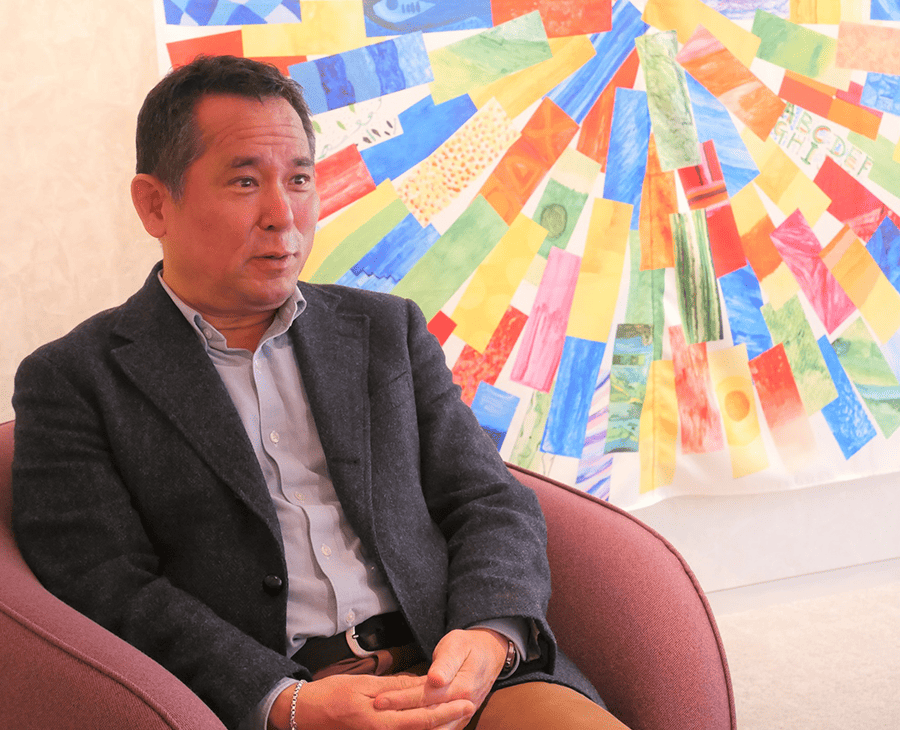
保険ビジネスはオペレーション業務も多いため、従来から積極的に間接費の削減や、システムを活用した効率化に力を入れてきました。いわゆる無駄を削減する、という文化は根付いている会社だと思います。人事も同様に実務が多い部署ですので、従来からBPOの検討を行ってきました。(伊藤様)
経営戦略の一環として、2017年頃、会社全体で業務効率化を実現するプロジェクトが立ち上がりました。人事でも業務を削減するためにBPOの検討に拍車がかかりました。BPO導入の大きな効果としては、人事業務の標準化が進んだことや例外対応を縮小できたことがあげられます。当社は例外対応が多く、過去の検討でもBPO導入に至らなかった原因の1つでしたが、トップダウンで覚悟を持って進めたことで最小化され、業務の効率化に繋がったと思います。(伊藤様)
エイチアールワンへのBPOの評価
大きな理由は、御社の充実したサービス体制とスタッフの思いの強さです。当時の導入責任者の情熱とホスピタリティは印象的でした。複雑な手続きや手間がかかる作業も、丁寧に対応し、一つひとつ解決していく企業姿勢に信頼を寄せました。(伊藤様)
そのような姿勢は、当社が運用フェーズに入ってからも実感しています。御社のスタッフはいつも親身になって対応してくれていますし、対話型のコンサルティングが好印象です。(伊藤様)
セキュリティなどの懸念は当然ありましたが、御社の株主や受託実績からも安心して任せられると思いました。またユーザー目線で言えば、従来と比較してサービスレベルが低下しないか、特に社員からの問合せ対応の品質については懸念の1つでしたが、今では御社を知らない社員はいないくらいに御社名は浸透していますし、大きな問題は発生していません。(伊藤様)
2020年頃、コロナ禍で、入社書類の完全ペーパレス化を進めている際に、良いご提案をいただけずに苦労した記憶があります。もしかすると当社の要望は少し時代を先取りしていたかも知れませんが、御社には、世の流れを先取りするくらいの積極性が欲しかったですね(笑)(伊藤様)
HROneに期待すること
AIを活用した新サービスを一緒に検討していただきたいですね。例えば、社員からの問合せについて、未だに当社に連絡が入ることがありますが、実務は御社に委託していることから、当社側では回答が出来ないことも多くあります。当社に入った質問でも、御社の回答と相違がない回答ができるなど、AIで対応できるようになると良いですね。(伊藤様)